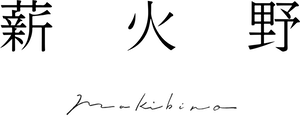いくつもの夜を越えて
1年は365日。毎日を朗らかに生きたいと願うけれど
そうもいかないのが現実ってやつだ。
でも食卓にとびきりのパンがあったらどうだろう。
日常の解像度をそっと上げてくれる
誰かと喜びを分かちあえるパンがあったら。
-
22歳の青年は世界を変えたいと願った。
一筋の灯を信じ、歩み続けてパン屋になった。
手で捏ねる、薪窯で焼く、そして届ける。
その一つひとつが愛しい人にふれるようにやさしい。
ああ、薪火野のパンが食べたくなってきた。
-
写真:大西文香、文:忠地七緒
毎日に寄り添う
丹波の山々が月明かりに照らされる頃、薪火野のパン作りは始まる。石臼で挽いた小麦粉と水を混ぜ、翌朝、発酵を終えた生地を整えていく。一本一本薪をくべ、中が真っ白に煤切れしたら窯入れどき。炎という命が生地に吹き込まれ、20分もすれば焼きたてのやさしい香りで厨房がいっぱいになる。
「僕のパン作りはとてもシンプルです。捏ねて発酵させて焼きあげるだけ。種類もカンパーニュ、ブレ、ブリオッシュなど小麦主体のパンに絞っています。それは小麦を未来につなぎたいという想いが根っこにあるから」
少し照れながら、でもはっきり口にするのは薪火野の中山大輔さん。薪火野のパンはどっしりとした風貌とは裏腹に強いくせがないからしみじみおいしい。チーズやワイン、魚や
肉料理、何と合わせてもうまみが引き立ち、少しずつ食べつないでいける“糧”のような存在だ。
「飲み干したあと何も残らない水のように、食べたあと何も残らないパンがいいと思っています。その方がまた食べたくなりませんか? 余分なものを削ぎ落とすことでみなさんの日々の食卓に寄り添いたいんです」
厨房には冷蔵庫やミキサーなどの機械もほとんどない。あるのは大きな石窯、石臼、麻の型、知人作家による木製ピールや照明。選びぬかれたそのどれもが薪火野のパンを形作っている。
「自分が豊かじゃないといいパンは焼けないので、使っていて心地よい道具を選ぶし、体と心が健やかな作り方を模索してようやくここまでたどり着きました。なんせ手ごねだから思いも体温も全部伝わっちゃうんです(笑)」
小麦から世界を変える
パン職人を志したのは大学の頃。入学直前に発生した東日本大震災の記憶が風化していく世の中に違和感を覚えた中山さん。転機となったのは学生プロジェクトで訪れた鹿児島の小さな離島・宝島での経験だった。
「街灯もコンビニもない場所での生活は“衣食住”を見つめ直すいい機会になりました。たとえば衣服をバナナの葉で染色したり、ヴィーガン料理を食べると体が軽かったり。でもその感動を大学の友人に伝えても真剣に聞いてもらえなくて。当時、経済や環境、食に関する現状に危機感を募らせて『世界を変えなきゃ』と強く感じていたけど、僕一人では何もできずモヤモヤしていました」
そんなある日、宝島でお世話になった農家から便りが届く。中身は彼らが育てていた名もなき小麦。これが人生を大きく変えることになる。
「農家さんの意思を残したいから小麦を途絶えさせたくないと思ったんです。ちょっとロマンチックな大学生だったんで(笑)とはいえ麦のままじゃ何もできないから”小麦粉”にするために迷わず石臼を買いました。オーストリアからわざわざ輸入して」
「今思い返しても高い買い物だったと思うんですけど」とはにかむ中山さん。挽いた小麦粉でパンやスコーンを焼きはじめ、そのうち小麦と水を混ぜ発酵させることで種をつなぐようになった。
就職活動時期だったが就職するイメージは持てなかった。「器用じゃないから一つを極めたい。種をつなぐのは無理なくできるし、国産の有機小麦をふんだんに使うパンを作ることは地球にもやさしい。その循環を大きくすることが世界を変えるために僕ができること。だからパン屋になろうと決めました」
目指すのは小麦を育て、手で捏ね、薪窯で焼くパン屋。欧米では伝統的なこの食習慣を日本に根付かせることで世の中を変えると決め、大学を中退した。

大事なものを見つけた旅
パン職人になるにはパン屋で修行し、独立を目指すのが一般的。中山さんも同じルートを辿ろうとしたが、どこに面接へ行っても「君はうちじゃない方がいい」と落とされ続けた。
「手ごねや薪窯で焼くパン屋は日本にほとんど無かったんです。唯一、理想とする製法で作っている広島の『ブーランジェリー・ドリアン』で3ヶ月研修した後、ヨーロッパに向かいました。日本でできることが限られているなら、小麦パンが主食として根ざすヨーロッパで学ぼうと思って」
フランス、スペイン、ポルトガルと1200kmもある巡礼路を踏破し、小麦農家での修行、ドイツやデンマークの視察など自らの五感でめいっぱい吸収した8ヶ月。印象的だったのはパンが風土に寄り添っていたこと。
「湿度の低いフランスではパリッとした固めのパン、魚介と合わせる機会の多いスペインでは味の濃い料理と相性が良い全粒粉パン。気候や食文化に合わせてパンそのものが変化する様子が自然で良いなと思って。僕も土地に根ざす根源的なおいしさを追求しようと決意が固まりました」
2018年の暮れに帰国し、開店準備にとりかかる。場所は兵庫県丹波市、薪火のパンだから名前は「薪火野」。四方を山で囲まれた小さなログハウスを見つけ、クラウドファンディングの応援をもとに薪窯を作りあげた。
そして2019年6月9日に待望のオープン。ただ営業はわずか22日間のみ、7月1日をもって薪火野は無期限休業に入った。

光はいつだってここに
「開店日に母のがんが発覚したんです。これから、というタイミングで実家に戻ることになりやむなく休業。お金もない、家族もどうなるか分からない、再開の目処も立たない、目の前が真っ暗になりました」
でも「いつかパンを焼く」という一筋の灯りだけはあった。遠くおぼろげだったけれど、確かにそこに光はあった。
「パンを焼くという希望を捨てなかったから今があると思います。あとは休業中、ふと耳にする音楽や友人とのたわいもない会話、応援してくれる方の言葉に助けられて…。暗闇だったからこそ、以前は気づけなかった日常の小さな喜びが際立って見えました」
闘病もむなしく12月に母は他界。今年2月、中山さんは丹波に戻り、早速パン作りを再開した。
「休業前よりパンが良くなっています。毎日たくさん焼いているし、心に余裕が生まれて自分のペースで作れるようになったから。今はいい意味でこだわりがないんです。おいしいって言われるのはうれしいけど、それよりパンを通じて日常の小さな光に目を向けてほしい」
「たとえば『明日の朝ごはん楽しみだね』『パンが届いたから一緒に料理しよう』という会話や、そこから生まれる暮らしも光だと思うんです。先の見えない世の中だけど、僕らの周りにはいつだって光があふれていて、薪火野が光を見つけるきっかけになれたら。そして食という営みに目を向ける機会にしてもらえたらうれしい。その繰り返しがいい未来につながると信じています」
未来へ、一歩一歩
東日本大震災から10年の月日が経とうとしている。小麦との出会い、ヨーロッパ修行、母の死。様々なことがあったが振り返ってみれば今日まで一本の道だった。そしてこれからも従来のパン屋像にとらわれない、自分だけの道を開拓していく。
「薪火野のパンは材料も製法もシンプルな分、僕が具材みたいなもので。僕自身がどんどん変わりゆくことでパンも成長していくのが楽しみ」
と少年のような顔で笑う。パンを焼く、だれかの日常に寄り添う、おいしさの先にある未来につながる、その循環がまたおいしいパン作りにつながる。自分ができることを一歩一歩。
「パンも窯作りも巡礼も本質は同じ。僕は自分の意思で進むことが生きがいだし、これからもその実感を追い求めていくと思います。歩みはゆっくりかもしれないけれど、足を前に進めていればいつか想いは形になる。実は本当に実現したい未来はもう少し先にあるから」
はじまりは“世界を変えたい”。でも結局行き着いたのは自分自身だった。僕が何をしたいか、僕が何をできるか。マイペースな歩みかもしれないがその姿に共鳴し、足跡をたどる人が増えていけば小さな革命になる。小さな革命はいつか大きな潮流になるのが冒険小説の定石だ。
薪火野の前には大きな欅の木が一本ある。欅は長い年月をかけてゆっくり高さを伸ばし、扇のように枝葉を茂らせていく。ふと欅の木と中山さんが重なって見えた。